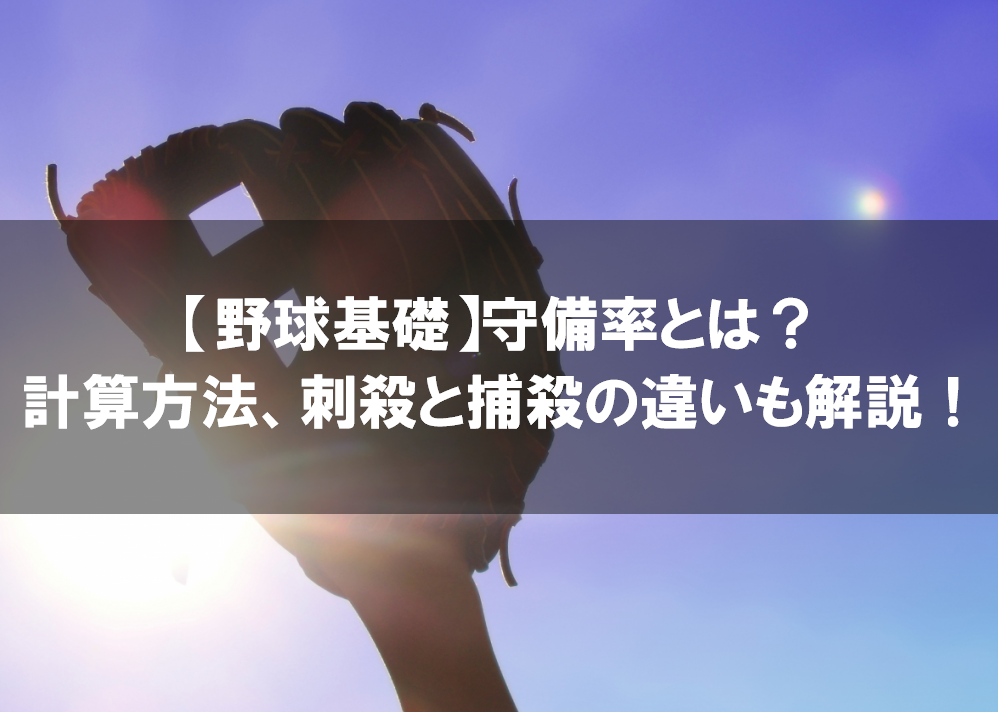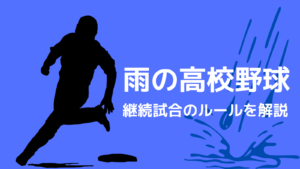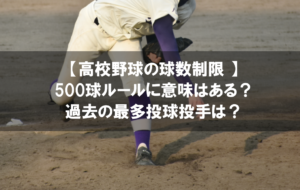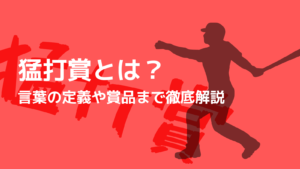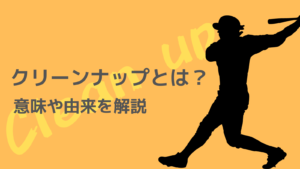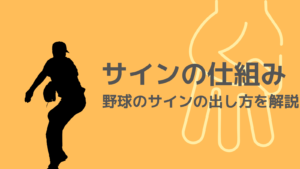当記事のテーマは守備率です。
野球観戦歴20年超の野球オタクで、元球場職員の経歴を持ちます。
愛読書は公認野球規則で、野球のルール解説も得意としています。
守備率とは?
守備率とは、守備機会に対してエラーをしなかった確率を指します。
エラー数がゼロの場合、守備率は1.00ですので、守備率の最大値は1.00です。
エラー数が多いほど守備率は下がりますので、守備率は高ければ高いほど良い指標と言えます。
守備率は日本プロ野球機構(NPB)によって記録・発表されている公式記録です。
守備率の計算方法
守備率の計算方法自体はシンプルですが、計算に使用する単語が少々難解ですね。
(刺殺数+補殺数)÷ 守備機会数
※守備機会 = 刺殺数 + 補殺数 + 失策数
簡単に理解するなら、守備率 = 「エラーをしなかった守備」÷ 守備機会と覚えてしまっても問題ありません。
要するに、守備機会の中でいくつアウトに出来ているか(エラーをしていないか)を算出しているのです。
ここでは、守備率を正確に理解するため、刺殺数と補殺数、そして失策数についても解説します。
刺殺数とは?
「刺殺」をシンプルに理解するには、そのアウトの中で最後にボールを触った人に記録されるものと理解しましょう。
刺殺が記録されるプレーとして、以下の通り定義されています。
• 飛球を捕球したことにより打者をアウトにしたとき
• 送球を受けて打者または走者をアウトにしたとき
• 塁を離れた走者への触球によりアウトにしたとき
誰に刺殺が記録されるか?については、そのアウトで最後にボールを触ったのは誰だ?と考えるのがシンプルでわかりやすいです。
具体例を挙げてみます。
ショートが打球をキャッチした時点でアウトが成立していますので、このアウトで最後にボールを触ったのはショートです。
そのため、ショートに刺殺が記録されます。
ランナー無しでショートゴロを打ったとしましょう。ショートがキャッチし、ファーストに送球することで打者はアウトになります。
この例では、最後にボールを触ったのはファーストなので、ファーストに刺殺が記録されます。
ランナー1塁の場面で走者が盗塁を仕掛け、キャッチャーが盗塁を刺したとします。
盗塁を刺したのはキャッチャーですが、最後にボールを触ったのはセカンドです。
この場合、刺殺はセカンドに記録されます。
三振で打者がアウトになった場合も刺殺は記録されています。
三振の場合は最後にボールを触ったのはキャッチャーですので、キャッチャーに刺殺が記録されるのです。
補殺数とは?
それでは、「補殺」とはどのような場合に記録されるのでしょうか。
補殺は、アウトが記録された場合に、関与したプレイヤー全てに記録されます。
ただし、最後にボールを触った(刺殺が記録される)選手には補殺は記録されません。
補殺はアウトの「補助」をした記録と覚えておくと良いでしょう。
こちらも具体例を見ながらイメージを深めましょう。
ライナーやフライでは補殺は記録されません(キャッチした選手に刺殺が記録されておわり)ので、内野ゴロの場合を考えてみましょう。
ランナー無しでショートゴロを打ったとしましょう。ショートがキャッチし、ファーストに送球することで打者はアウトになります。
この例では、最後にボールを触ったのはファーストなので、ファーストに刺殺が記録されましたよね。
ここでアウトの補助をしているのが、送球したショートです。
このプレーではショートに補殺1、ファーストに刺殺1が記録されるのですね。
少々複雑になるのがゲッツーの場合です。
セカンド、ショート、ファーストと渡る4-6-3のダブルプレーか成立したとしましょう。
- 1つ目のアウトで最後にボールを触ったのはショートなので、まずショートに刺殺1が記録されます。
- 1つ目のアウトで補助しているのは送球したセカンドなので、セカンドに補殺1が記録されます。
- 2つ目のアウトで最後にボールを触ったのはファーストなので、ファーストにも刺殺が記録されます。
- 2つ目のアウトで補助しているのは送球したショートなので、ショートに補殺1が記録されます。
このプレーで選手別に刺殺と補殺をまとめると以下のようになります。
- ファースト刺殺1
- セカンド補殺1
- ショート補殺1刺殺1
1つのプレーで、ショートには刺殺も補殺も両方が記録されるのですね。
刺殺と補殺はあくまでも1つのアウトの中で考えますので、ダブルプレーなどではこのような現象が発生します。
失策数とは?
失策数は簡単で、エラーした数です。
ミスによってアウトがセーフになってしまった場合や、ランナーの進塁を許してしまった場合にエラー(失策)が記録されます。
守備率で守備力は測れない!?UZRとは?
守備率はあくまでもエラー数を元に算出する数値ですので、守備率で守備力を測ることは出来ないという意見が大きくなっています。
守備範囲が広いあまり、厳しい打球にも追いつける選手は難しいプレーが増え、エラー数は増えてしまいます。
このような選手はエラー数が多くなるので守備率は低くなりますが、だからといってこの選手の守備力が低いと言えるでしょうか。
こういった疑問から、守備率を重視しない見方が広がってきているのです。
守備率に変わって、近年注目を集めているのがセイバーメトリクスのひとつであるUZR(アルティメット・ゾーン・レーティング)です。

選手の守備範囲などを踏まえて算出される指標で、守備率よりも信頼性が高いと見られています。
守備率まとめ
ここまでの内容を箇条書きでまとめます。
- 守備率 = 「エラーをしなかった守備」÷ 守備機会
- 計算式は(刺殺数+補殺数)÷ 守備機会数
- 刺殺とはそのアウトの中で最後にボールを触った選手に記録されるもの
- 補殺とはそのアウトを取る上で補助した選手に記録されるもの
- 近年は守備率よりもUZR重視