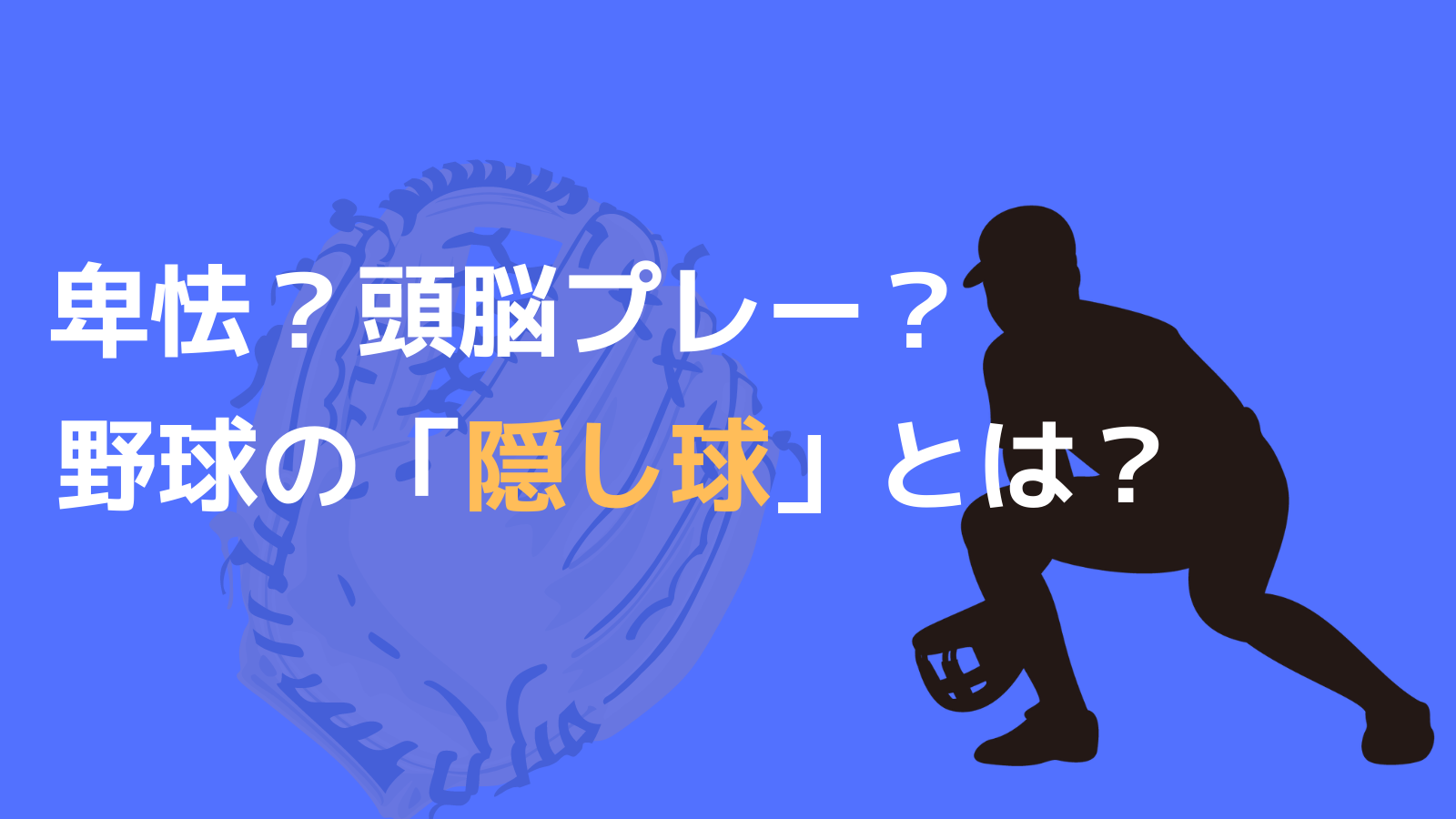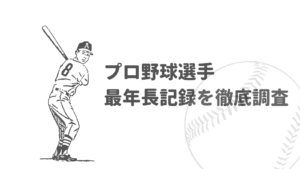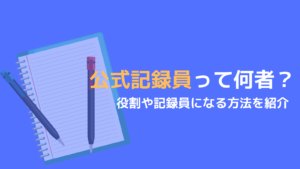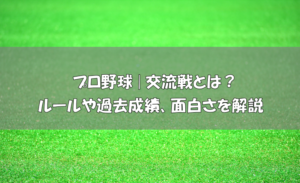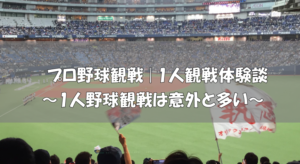当記事では、野球のトリックプレー「隠し球」について解説します。
隠し球を成功させるための注意点や過去の事例を紹介しつつ、隠し球が激減した背景を解説します。
筆者のプロフィール
野球観戦歴20年超の野球オタクで、元球場職員の経歴を持ちます。
愛読書は公認野球規則で、野球のルール解説も得意としています。
目次
野球のトリックプレー「隠し球」とは?
まずは用語の定義について確認しておきましょう。
「隠し球」は古くから使われる野球用語ですが、これは正式にルールに定められた用語ではありません。
一般的に隠し球の意味は以下のとおりです。
隠し球とは
野手がボールを隠し持ち、走者が塁から離れたタイミングを狙ってタッチアウトを狙うプレー
走者だけではなく、相手のランナーコーチの目を盗む必要もある高度なプレーです。
パ・リーグの公式動画として、2009年のプレーが残っていましたので以下の動画をご覧ください。(ただ、決定的瞬間は残念ながらカメラマンでも捉えられていません・・)